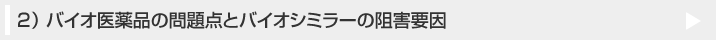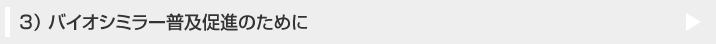バイオ医薬品の登場で寛解率が飛躍的に高まり、ここ数年でバイオシミラーが続々と発売されている関節リウマチ。患者数は60万~100万人に上り、バイオシミラーへの切り替えが進むと医療費削減へのインパクトが非常に大きいと言われています。一方で先行バイオ医薬品からバイオシミラーへの切り替えには、医療関係者の理解と協力が、より重要な要因となっています。
今回は、東京女子医科大学病院膠原病リウマチ痛風センター所長で、東京女子医科大学膠原病リウマチ内科学講座教授・講座主任の山中寿先生に、実臨床の現場に立たれる医師の立場からみたバイオシミラーの使用状況、患者さんの反応、バイオシミラーへの切り替えに対する課題・問題点、さらに普及に向けた提言をいただきます。(対談日:2019年3月15日)
※所属・役職は対談当時のものです。
関節リウマチ治療の進歩とEBM
リウマチ治療を大きく変えたバイオ医薬品
黒川
私が関節リウマチ(RA)に少し触れることができましたのは、厚生省(現、厚生労働省)勤務時代、慶應大学医学部の教授でいらした本間光夫先生に、医薬品の安全性関係でお世話になっておりましたときのことです。当時は、抗リウマチ薬の金製剤―例えばシオゾールや、痛み止めしかなく、私も十分な知識がないものですから、「先生、リウマチとはそんなに難しい病気ですか」と伺ったところ、「いや、黒川さん、本当に深刻な病気なのですよ。よくなったり悪くなったりして、だんだん患者さんは動けなくなってしまいます」とおっしゃったことを印象深く覚えております。
山中先生は現在、月間外来患者数が11,000人に達する日本最大規模の東京女子医科大学病院膠原病リウマチ痛風センターの所長を務めておられますが、最初からリウマチを専門とされていらしたのでしょうか。
山中
はい、1980年に三重大学を卒業し、すぐにリウマチの世界に入りました。1983年に、当時の東京女子医大のリウマチ痛風センター、今の膠原病リウマチ痛風センターができたときに東京へ参りまして、以来ずっと東京女子医大でリウマチの診療に取り組んでいます。
その頃は、今言われたように、金製剤とD-ペニシラミン製剤の2つしか薬がありませんでした。リウマチは自然に進行していく病気ですので、そういった抗リウマチ薬を使い、少しでも進行を遅らせ、進行してしまったら整形外科の先生に手術していただいておりました。ですから、内科の先生でリウマチを専門にする人はほとんどおらず、リウマチ患者さんの症状が悪くなるのを待って、整形外科の先生が手術をしていた。そんな状態だったと思います。
そういう中で本間光夫先生は、内科としてリウマチや膠原病に先進的に取り組まれていた非常に偉大な先生です。本間先生のお弟子さんに柏崎禎夫先生がいらっしゃり、その先生がわれわれのセンターの2代目の所長になられ、私は柏崎先生の影響でリウマチの臨床研究を始めました。メトトレキサート製剤を開発しているときも、柏崎先生を中心に、私もお手伝いさせていただき、当時メトトレキサートは2.5mg製剤でしたが、製品としては2mg製剤の方が適切であることがわかり、治験にも関わって参りました。
メトトレキサート製剤は出てきたけれども、その使い方もまだ十分に熟知されていない。関節リウマチの治療法はまだまだこれからよくなるだろう。そういう期待だけあった時代だと思います。
黒川 そして、何と言ってもエポックは、20世紀の終わりから21世紀にかけ、バイオ医薬品のインフリキシマブ製剤(抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤)が登場し、標準治療のコースがガラッと変わったことでしょうか。寛解率が50%を超えたという数字を見て、医学の進歩、そして生命科学の進歩を感じた記憶があります。
EBMもリウマチ治療の前進に寄与
山中
おっしゃる通り、2002年にインフリキシマブ製剤が発売され、2003年に関節リウマチに適用拡大されて、関節リウマチの治療が大きく変わりました。ただ、インフリキシマブ製剤のような分子標的薬が出てきたのは、基礎研究の進歩が最初にあったわけで、リウマチの症状を悪くしているのがTNFαという分子であることが分かってきて、治療の新しいストラテジーが出てきた。そういう基礎研究の成果が患者さんの利益に結び付いている。トランスレーショナルメディシン(基礎と臨床を結びつける医学)としては、非常に画期的な発見というか、開発ではなかったかと思います。
それと、もう一つ忘れてはいけないのが、機を同じくしてEBM(Evidence Based Medicine:科学的根拠に基づく医療)が発達してきたことです。EBMも、ちょうどリウマチの治療法と同じぐらいのスピードで進歩してきました。インフリキシマブ製剤をはじめバイオ医薬品の開発の経緯、その臨床応用、それからその後の安全性の評価も含め、EBMの概念が非常に役に立ったのです。それで、現在の臨床医、特に若いドクターは、EBMの中で育ってきた人たちで、有効性も安全性もエビデンスベースで考える先生方が非常に増えてきています。
インフリキシマブ製剤の導入時に感染症、特に日本においては結核が増えるのではないか、という懸念がありました。インフリキシマブの使用は、日本よりもヨーロッパの方が早かったのですが、スペインでは結核が爆発的に増えたのです。発症が100倍以上になったと言われています。
黒川 厚生労働省も非常に危機感があったと思います。特に、日本はスペインと同程度の結核有病率とのことですし、歴史的に見れば、「国民病」と言われた病気でしたから。
山中
厚労省はそのことを非常に危惧し、インフリキシマブ製剤が発売されるときに、全例の市販後調査(PMS)の実施、つまり全症例を登録して安全性を検証しようという試みが始まったのです。それは関節リウマチ治療薬では前例のないことだったのですが、結果的に見ると、EBMの流れにも乗り、非常に有効に働きました。どうすれば結核を防げるのかということがわかり、スクリーニングをまずしよう、場合によってはイソニアジド(結核化学療法剤)の予防投与をしよう。そういうことでインフリキシマブは、最初の1,000例より次の1,000例、さらに次の1,000例と1,000例ごとに統計を取ると、結核の発症率が急激に減ってきました。PMSを行うことで安全な医療が確立できるのだということがわかったように思います。
それが、次のエタネルセプトにも、その後のアダリムマブ、トシリズマブにも、ずっと受け継がれ、現在の日本のリウマチ診療におけるバイオ医薬品の安全性が担保されてきました。それにより、臨床医も患者さんも安心してバイオ医薬品が使えるような環境ができてきたと言えます。
黒川 それが関節リウマチ患者を対象とした東京女子医大の前向き大規模コホート調査、「IORRA(Institute of Rheumatology, Rheumatoid Arthritis)調査」につながるのですね。
山中
はい。それで現在、リウマチの患者さんがいい状態で診療できるようになりました。東京女子医大の膠原病リウマチ痛風センターでは、約6,000人のリウマチ患者さんを診ています。日本にリウマチ患者さんは60万人、全国の患者さんの100人に1人はわれわれのところで診療している。それだけたくさんの患者さんをお預かりしている組織の責任として、データをきちんと集め、論文を書き、情報発信しようと考えており、2000年から「J-ARAMIS(Japanese Arthritis Rheumatism and Aging Medical Information System)調査」、今は「IORRA調査」と言いますが、コホート研究を始めました。
6,000人の患者さんに対して、年2回の調査を19年間続けています。約30ページの調査用紙をお渡しして、記入してもらい、郵送で回収しますが、毎回98%以上の患者さんから返答をいただいています。それが19年続いており、奇跡的な回収率と継続期間だと感じております。

「IORRA」ウェブサイト
http://www.twmu.ac.jp/IOR/recruit/iorra.html
黒川 素晴らしい回収率ですね。治験よりよいのではないでしょうか。
山中
そうなんです。どうして回収率がよいのか。もちろんシステムの問題もありますが、やはり患者さんの「よくなりたい」という思いでしょう。調査に協力することにより、自分たちの診療がよくなるのではないか。そういうことを期待されているのだと思います。当然、われわれにも「よくしたい」という強い思いがあるので、今まで140編以上の論文をそのコホート研究から出し、先ほど申し上げたEBMの流れを加速することに貢献できたと思います。
そういった環境の中、バイオ医薬品が浸透してきました。現在では、われわれのところで25%ぐらいの患者さんが、何らかのバイオ医薬品を使っています。そして、リウマチの寛解率は、2000年の段階では患者さん全体の8%しかなかったのですが、現在は57%ぐらいです。低疾患活動性(病気の進行度や症状、患者さんの機能障害の程度が低い状態)の患者さんも含めると、全体の75%がいい状態でコントロールされている。2000年代の寛解率の向上は、おそらくメトトレキサート製剤が寄与したところが大きいと思いますが、さらに2010年以降、バイオ医薬品が十分に使われるようになってから寛解率はすさまじく伸びました。基礎医学の進歩が薬剤の開発に結び付き、それが臨床応用され、エビデンスが明確になり、使われるようになった。非常にいいプロトタイプになったと思います。ただ、一方でいろいろ問題もあり、その辺りがバイオシミラーの話につながってくると思います。
●山中 寿(やまなか ひさし)
1980年三重大学医学部卒業、同大学第三内科入局。1983年より東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センターに勤務。2003年同センター教授、2008年同センター所長に就任。その間の1985~1988年米国スクリプス・クリニック研究所研究員。2019年5月に山王メディカルセンターリウマチ・痛風・膠原病センター長、国際医療福祉大学臨床医学研究センター教授および東京女子医科大学客員教授に就任。2000年「日本痛風・核酸代謝学会賞」、2012年には2000年から取り組んでいる関節リウマチ患者を対象とした前向き大規模コホート調査「IORRA」の実績により、2012年度「日本リウマチ学会賞」を受賞。
●黒川 達夫(くろかわ たつお)
1973年千葉大学薬学部卒業後、厚生省(当時)入省。薬務局 監視指導課等を経て、WHO職員。その後、科学技術庁、厚生省大臣官房国際課、医薬品審査、安全対策課長、大臣官房審議官等を歴任。2008年より千葉大学大学院薬学研究院特任教授、2011年から2016年慶應義塾大学薬学部大学院薬学研究科教授。2016年より日本バイオシミラー協議会理事長。薬学博士。