「炎症性腸疾患におけるバイオ医薬品の位置づけと
バイオシミラー普及に必要なこと」


さまざまなメディアを通じて「ジェネリック」の認知度が上がる中、「バイオシミラー」は知らない、聞いたこともないという患者さんや一般の方々はまだまだ多いように感じます。バイオシミラーについて理解し、納得して選択していただくためには何が必要か。今回は兵庫医科大学 炎症性腸疾患センター内科 診療部長の渡辺憲治先生にお越しいただき、炎症性腸疾患におけるバイオシミラーの使用経験に基づく情報提供のあり方について、お話しを伺いました。
(対談日:2020年12月4日)
※所属・役職は対談当時のものです。
炎症性腸疾患とバイオ医薬品の位置づけ

黒川 渡辺先生は炎症性腸疾患(以下、IBD)のご専門でいらっしゃいますが、まずIBDについて教えてください。
渡辺 この病気は、青年期に発症することが多い慢性疾患です。主なものは潰瘍性大腸炎とクローン病で、どちらも国が「指定難病」として医療費助成制度の対象にしています。日本の患者数は、潰瘍性大腸炎が20~21万人、クローン病が8~9万人で、年々増加しています。最近のAmerican Journal of Gastroenterology誌のeditorial reviewには、IBDは欧米人に多いとされていた疾患でしたが、欧米では患者数が頭打ちになる一方で、アジア、アフリカ、南米で増加しており、もはやglobal diseaseになったと記載されています。今の世界的な人口動態を考えると、いずれアジアは世界で最もIBD患者の多い地域となりそうです。
黒川 青年期に発症することが多いということですが、社会生活への影響が大きいのではないでしょうか。
渡辺 慢性疾患ですので、患者さんは社会的にさまざまな制限を受けます。女性では、結婚、出産などに不安を抱く患者さんが多くいらっしゃいます。ただ、近年の治療法の進歩で、このような心配を抱えることなく日常生活を送れるようになってきています。
黒川 IBDの治療は、どのように変わってきたのでしょうか。
渡辺 私がIBDの分野に携わり始めた頃は治療選択肢が少なく、特にクローン病では、病状が悪化すると入院して絶食、中心静脈栄養を1~2ヵ月は行わなければなりませんでした。長期入院を繰り返しますので会社から解雇されたり、学業を続けられなくなったり、中にはそれがつらくてうつ状態になってしまう患者さんもいました。その後、さまざまな薬剤が開発されて治療法も進歩してきたのですが、大きな転機となったのはバイオ医薬品のインフリキシマブが承認された2002年です。それに続く様々な新規薬剤の登場は、間違いなくIBD患者さんの予後向上に大きく寄与したと言えます。今では、以前のように急に悪化して、緊急入院や緊急手術など不測の事態に陥る頻度は随分少なくなりました。多くの患者さんが外来での診療によって一般の方とほぼ同じ生活を送れるようになってきており、逆に病状が良いために通院しなくなってしまうことが心配、というところまできていると感じています。
黒川 バイオ医薬品が、IBD患者さんに大きく貢献できたことはうれしいことです。ところで、バイオ医薬品は高額で、その使用は医療費全体を押し上げるため問題視する向きもあります。しかしながら、青年期に発症する慢性疾患を治療する上で必要かつ画期的な薬剤という観点に立つと、バイオ医薬品の位置づけについて全く違った景色が見えてくると思います。
渡辺 非常に重要な視点です。実は、日本はバイオ医薬品を使いすぎるという批判が一部にあります。IBDは指定難病で医療費助成があるため、自己負担が増加しないことをいいことに、高価なバイオ医薬品を医師も患者も安易に使っているという見方です。しかしながら、例えばインフリキシマブで改善した患者さんが仕事への復帰を果たした結果、社会的な生産性にどのような影響を及ぼしたか、あるいは入院や手術を回避できたことが医療費をどの程度軽減させたかなどのcost effectivenessがこの薬剤を評価する上で重要であり、実際には入院や手術の回避により総合的な医療費を抑制したとの報告も出ています。また、バイオ医薬品といえども、狭窄や瘻孔(ろうこう)といった合併症を発現するほど病勢が悪化した段階で使用しても、思うような効果は得られにくいのです。使うべきタイミングというものがあって、使うべきときに使える日本の制度は医療従事者としては助かっており、少なくとも多くの専門家は個々の患者さんの病状に応じて、適切な時期にバイオ医薬品を導入していると思います。
先行バイオ医薬品とバイオシミラーの役割

黒川 厚生労働省は、2018年度国民医療費は43兆3949億円、伸び率は前年度比+0.8%と公表しています。このような状況の中、IBDの患者数は増加の一途をたどり、高額なバイオ医薬品が増えていますので、安価なバイオシミラーが活用されることで財政面に少しでも寄与できればと考えています。
渡辺
同感です。今年は新型コロナウイルス感染症の影響もあるのですが、それ以前から病院は医療提供体制だけでなく経営的にも逼迫していました。財源に限りのある中、医療費の適正配分は必須ですし、先行バイオ医薬品をバイオシミラーに切り替えるという選択肢は必要だと思います。
インフリキシマブのバイオシミラーが初めて登場したときのことを思い出しますと、IBDについては「外挿」により適応取得となりましたが、当時はそれをすんなりと受け入れることができませんでした。しかしながらバイオシミラーもIBD以外の疾患では新薬と同じような治験を行っていますし、先行バイオ医薬品と同等であるとする臨床試験も多数報告されています。バイオシミラーに関しては、われわれ医療従事者がもっと理解しなければならないと考えています。
その一方で、IBDでは病態の多様性に対して異なる作用機序の薬剤を必要としますので、これからも新薬を求め続けていきます。黒川理事長に伺いたいのですが、日本も含めてバイオシミラーの使用割合が世界的に高まっていくことは間違いない状況ですが、このような中で、新薬開発企業とバイオシミラー開発企業は共存共栄できるのでしょうか。
黒川 新薬開発企業は、最初から国際展開を視野に活動します。その過程において製造販売承認申請先の国の許認可制度を考慮し、自社の科学的成果を広く提供できる環境を整えて市場に参入し、研究開発にかけた費用は知的財産権の保護期間中に回収するとともに、その知見をベースに新たな薬剤の研究開発を手がけます。一方、バイオシミラー開発企業は、先行バイオ医薬品の知的財産権保護期間が終了し有用性が確立された薬剤について、同等性/同質性が担保されたバイオシミラーとしてあまねく、安価で、安定的かつ持続的に市場に提供します。両者とも、有用な薬剤を患者さんに届けるという目的は一致していますし、それぞれが得意な分野での責務を果たしていることから、このような棲み分けもごく自然なものと言えます。
渡辺 明快なお答えをいただき、ありがとうございます。
IBD領域でバイオシミラーを普及するために必要なこと
黒川 IBDには指定難病の医療費助成制度がありますが、バイオシミラーを使用した場合の患者さんの医療費自己負担額への影響はいかがでしょうか。
渡辺 先程も少し触れましたが、通常の保険診療に比べて、IBDでは医療費助成制度により自己負担の上限額が非常に低いため、バイオシミラーに切り替えたからといって自己負担額が軽減するケースは少ないです。また、日本は医療に対するフリーアクセス権を保証する独特のシステムを採用しており、患者さんは自分で病院を選び、自分で治療を選択することが可能です。国民医療費全体の適正化を目指して、先行バイオ医薬品ではなくバイオシミラーを選ぶというモチベーションをIBD領域では持ちにくい環境にあると言えます。
黒川 そのような中、バイオシミラーを患者さんに提示する際、渡辺先生はどのような点に留意されていますか。
渡辺 冒頭にお話ししましたように、IBDは青年期に発症することが多く、長期にわたる経過をたどる慢性疾患ですので、医師と患者さんの信頼関係が極めて重要となります。身も蓋もない話になるかも知れませんが、詰まるところ、信頼を置いている主治医の勧めであれば患者さんはバイオシミラーを素直に受け入れると思います。これが一番の要因でしょうね。
黒川 渡辺先生が、患者さんとの信頼関係が大切とされているからこそのお答えだと思います。バイオシミラーに切り替えて、印象に残ったエピソードはありますでしょうか。
渡辺 一番いいのは、切り替えたときに何も起こらないことです。患者さんから何も質問されない、不安が示されない、バイオシミラーに切り替えたことが診察の場の話題に上らないのが一番望ましい状況だと考えています。
黒川
我々は何か話題を求めがちですが、おっしゃるように臨床においては話題にならないことが1番望ましいのかもしれません。
最後にお伺いしたいのですが、以前に比べましてバイオシミラーへの理解が進んでいると考えているものの、まだまだ不十分ですし、患者さんや一般の方への認知度は低いです。先生方のサポートを行う立場の私共に何か期待されることはありますでしょうか。
渡辺
患者さんがバイオシミラーについて詳しく知らなければ当然のことながら不安を抱くでしょうから、その不安を解消するために理解の進むパンフレットなどがあるとよいと思います。外来は多忙ですから、医師が説明するにも限界があります。患者さんが待ち時間などに目を通せる資料を作成して頂き、診察室に入ってこられたら主治医にわからないことを質問するというシステムにすれば、診療もバイオシミラーへの切り替えも円滑に進むと思います。
また、バイオシミラーに切り替えたタイミングで、たまたま患者さんが気になる症状があると、患者さんはそこに因果関係を求めがちです。そのときの対応は大体2つのパターンに分けられます。実際のところはバイオシミラーへの切り替えと患者さんの訴えは無関係なのですが、1つは「関係ないと思いますから、このまま続けましょう」と医療従事者が御説明するパターン。もう1つは「では、元の薬に戻しましょう」と御説明するパターンです。後者のパターンには、医療従事者本人がバイオシミラーに切り替えたことに伴うリスクを回避したいという心持ちが現れている場合も含まれます。背景にバイオシミラーに対する認識不足などの問題が隠れているのかも知れませんが、患者さんが不安を訴えたり、疑問を呈したりしたとき、医療従事者は安易に自らのリスク回避に走るのではなく、その原因が何かに真摯に向き合って、解決に向かって患者さんと共に歩まねばなりません。そのときに参考となる資料を医療従事者に提供することも、バイオシミラーについての患者さんの理解を進める上で役に立つと考えます。
黒川 貴重なご助言をありがとうございます。医療従事者の方々、患者さんと一般の方々にバイオシミラーを知っていただくために、今のご意見を活かして参りたいと思います。本日は貴重なお考えを伺わせていただき、ありがとうございました。
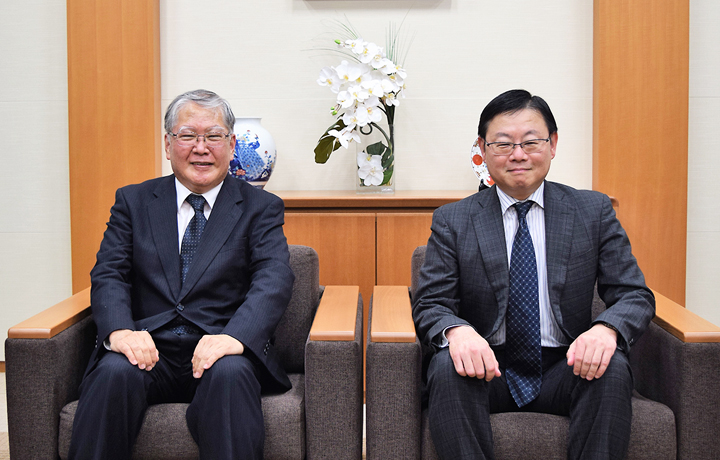
●渡辺 憲治(わたなべ けんじ)
1991年秋田大学医学部卒業。大阪市立大学医学部附属病院消化器内科講師、大阪市立総合医療センター消化器内科副部長を経て、2014月より大阪市立大学医学研究科消化器内科学客員准教授、2017年より兵庫医科大学腸管病態解析学特任准教授、2020年より同大学炎症性腸疾患センター内科准教授・診療部長に就任。日本消化器病学会財団評議員・専門医・指導医、厚労省「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」班(鈴木康夫班長)研究協力者/治療指針・診断指針プロジェクト委員、炎症性腸疾患ガイドライン委員他。
●黒川 達夫(くろかわ たつお)
1973年千葉大学薬学部卒業後、厚生省(当時)入省。薬務局 監視指導課等を経て、WHO職員。その後、科学技術庁、厚生省大臣官房国際課、医薬品審査、安全対策課長、大臣官房審議官等を歴任。2008年より千葉大学大学院薬学研究院特任教授、2011年から2016年慶應義塾大学薬学部大学院薬学研究科教授。2016年より日本バイオシミラー協議会理事長。薬学博士。
